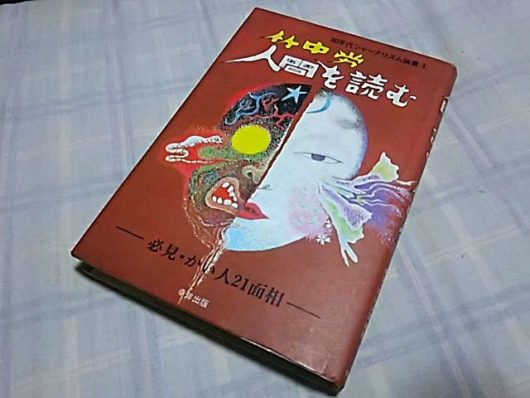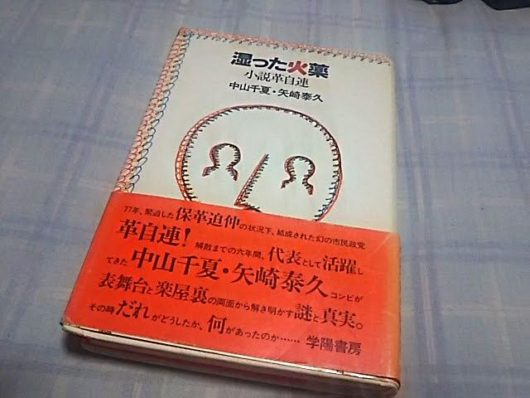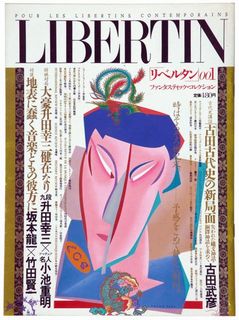インターネットの社会において、必ず騒動を巻き起こすキーワードというものが存在します。一つは思想的な左右に関するもので、「ウヨ(右翼)」「サヨ(左翼)」に派生して様々な言葉があります。また日本における民族問題を象徴するような沖縄に住む人や在日韓国朝鮮人をやゆするような言葉、さらにあるのが今回の題材である宗教に絡む特定の団体についての言葉、その中でも「創価学会」に反感を持っている人によって書かれた言葉もネット上にはあふれています。
ここで、ちょっと竹中労さんにからめてそれらの言葉を眺めてみると、竹中労さんが活躍していた当時は保守勢力からは左翼過激派の黒幕と目され、反対に一部の左翼からは竹中労は右翼と結託したと言われていました。さらに在韓被爆者についてのルポルタージュを書くなど、在日韓国朝鮮人に寄り添った活動もし、当然沖縄には過分な思い入れがありました。週刊誌報道で創価学会についての醜聞が書かれた事についてその反論記事を書き連ねたり、今回紹介する創価学会の初期の学会員に取材した「聞書 庶民列伝」を月刊誌「潮」に連載するなど、竹中労は創価学会に取り込まれたのではと思う人がいても仕方がないような活動もされてきたのです。そういう意味では誰からも叩かれる材料を広く拡散させながら色々な仕事をしてきたわけで、そのエネルギーには私などはただひれ伏すしかありません。
過去の竹中労さんの書かれたものを読むと、反創価学会キャンペーンを展開した人々を大いに批判し、さらにそうした文章の中には創価学会の池田大作会長を褒め称えるかのような内容があることから、創価学会に拒否反応を示す人からすると、まさに創価学会に取り込まれた御用ライターという一面もあったのかというような印象を持っている人もいるかも知れません。
ただ、そこまで創価学会に食い込んでいればもう少しお金は入っていたでしょうし、その後の書くものも変わっていたと思われます。竹中労さん自身は「アナーキスト」と称していますが、世間一般が言う所の「アナーキスト」とはずれているかも知れませんが、どんな権威にも屈せずに言いたいことを言う自由な精神を持って「聞書 庶民列伝」を含む創価学会にも対してきたのではないかと私は思っています。
そもそもこの「聞書 庶民列伝」という書物はどういう書物かというと、現在の大掛りに組織された創価学会ではなく、かなり過激に活動をしていた初期の創価学会の活動について、創価学会初代会長・牧口常三郎についての話や、当時の最前線で活動していた学会員に取材したルポルタージュとでも言うべきものです。そこにあるのは、原点回帰と言うべきものなのか、創価学会ができた当時の過激な行動を思い出せというメッセージそのものです。
当時はあまり外から創価学会を見ている分には、創価学会と公明党の関係を見るにつけ、その結びつきは強いと思うばかりで、竹中労さんのやっていることがいまいち良くわからないという人もいたかも知れません。しかし、公明党が自民党との連立内閣に入り、創価学会が主張している不戦世界を目指すことや、核兵器廃絶という理念を破りかねないような選択に公明党が舵を切りつつある中、創価学会の一般会員の中でも政府の安保法制に反対するデモに参加するような「造反者」が出るようになりました。「上に向かって堕落」するかのような党中央への批判の眼を持ちつつ、逆に一般の学会員には共感し、庶民信仰には味方すると言い、創価学会が結成された時の理念に戻れと会員を鼓舞する竹中労さんの思想というのは、現在の創価学会の会員の中にも理解する方は少なからずいるのではないかと思われます。
竹中労さんは何をやった人かということを明らかにするのがこのブログのテーマでもあるのですが、ルボルタージュをはじめとする物書きである以外に社会を変革する運動家としての面があったという事は確かです。意地悪な見方をすると党中央や創価学会の幹部は批判するのに、なぜ池田大作会長だけを持ち上げているのか、やっぱり何かあるのかと思われるのかも知れませんが、他の大勢で決まったことであっても、会長さえ動かすことができれば状況は変わると考えての運動家らしい工作だったかも知れません。まあ、この点については、創価学会も自分らをうまく書いてくれるルポライターだと竹中労さんの事を思っていたのかも知れませんし、この辺の駆け引きというのは興味深いですね。
その後の創価学会は、先述の通り当時の若手であった人達が中心となり、政権の中にいることこそが大事だという方向に進み、公明党も創価学会も創価学会の原点にある考えとは違った行動を取ろうとしています。竹中労さんがもし今でも健在だとしたら、組識の中枢にいる人よりも、自由な発言を封じられた中で行動を起こした造反者の方に温かい眼差しを掛けたことでしょう。